第1 事業者が行う退避や立入禁止等の措置
令和7年4月1日から、事業者が「労働者」に対して行う退避や立入禁止等の措置の対象者が、「同じ場所で作業を行う全ての作業者」に拡大されました。この改正により、以下の1、2の人(個人事業者、他社の労働者、資材搬入業者など、契約関係の有無は問わない)に対しても保護措置の実施が義務付けられました。
1危険箇所等で作業に従事する労働者以外の人
2危険箇所等で行う作業の一部を請け負わせる個人事業者等
対象となる条文は、次の4省令において、作業場所に起因する危険性への対処(退避、危険箇所への立入禁止等、火気使用禁止、悪天候時の作業禁止)を規定する条文(労働安全衛生法第20条、第21条、第25条及び第25条の2根拠)です。
・労働安全衛生規則 ・ボイラー及び圧力容器安全規則 ・クレーン等安全規則
・ゴンドラ安全規則
改正のポイントとQ&Aはこちら
主な改正内容
1危険箇所等において行う以下の措置の対象者を、「労働者」から「作業に従事する者」に拡大
(1)危険箇所等への立入禁止、危険箇所等への搭乗禁止、立入等が可能な箇所の限定、悪天候時の作業禁止の措置
(2)喫煙等の火気使用が禁止されている場所における火気使用の禁止
(3)事故発生時等の退避
2危険箇所等で行う作業の一部を請け負わせる個人事業者等に対する周知の義務化
危険箇所等で行う作業の一部を請負人(個人事業者、下請業者)に行わせる場合であって、立入禁止とする必要があるような危険箇所等において、例外的に作業を行わせるために労働者に保護具等を使用させる義務がある場合には、請負人(個人事業者、下請業者)に対しても保護具等を使用する必要がある旨を周知する措置が義務づけられます。
重 要 事 項
今回の改正における義務付けの対象ではありませんが、以下の(1)、(2)に示すような場面については、事業者が作業の一部を請け負わせた請負人に対して、保護具等の使用が必要である旨や、特定の作業手順、作業方法によらなければならない旨を周知することが推奨されます。
(1)作業に応じた適切な保護具等を労働者に使用させることが義務付けられている場面
(例)最大積載量2t以上5t未満で、テールゲートリフター(TGL)が設置されている貨物自動車でテールゲートリフターで荷の積卸しを行うとき。
(2)特定の作業手順や作業方法によって作業を行わせることが義務付けられている場面
(例)最大積載量が2t以上の貨物自動車で荷を積み卸す作業を行うときの、昇降設備の設置。
令和7年4月改正の要点は、
1危険箇所等で作業に従事する労働者以外の者
2危険箇所等で行う作業の一部を請け負わせる個人事業者等を対象とする保護措置を事業者に義務付ける。
というものです。
義務付けられた保護措置は次のとおりです。
- 危険個所等への立入禁止
- 危険個所等への搭乗禁止
- 立入り等が可能な個所への限定
- 悪天候時の作業禁止
これらの保護措置実施対象者は、改正前は作業場に直接雇用される「労働者」のみでしたが、改正により対象者が拡大し、「作業場で何らかの作業に従事する全ての者」に対しても措置が義務付けられました。
労働安全衛生規則
(立入禁止)
第151条の9
事業者は、車両系荷役運搬機械等(構造上、フォーク、ショベル、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)を使用する作業場において作業に従事する者がそのフォーク、ショベル、アーム等又はこれらにより支持されている荷の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、フォーク、ショベル、アーム等が不意に降下することによる危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させるとき(当該作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させ、かつ、当該請負人に対し、安全支柱、安全ブロック等を使用する必要がある旨を周知させるとき)は、この限りでない。
2前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。
労働安全衛生規則
(立入禁止)
第433条 事業者は、はい付け又ははいくずしの作業が行われている箇所で、はいの崩壊又は荷の落下により危険を及ぼすおそれのあるところに、当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
クレーン等安全規則
(立入禁止)
第28条 事業者は、ケーブルクレーンを用いて作業を行うときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは横行用ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳ね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
【解説】
1事業者は、労働者に対して、特定の場所への立入禁止、特定の箇所への搭乗禁止、事故等発生時の退避、退避に関連する措置、悪天候時の作業禁止、表示による必要事項の周知を行う義務がありますが、これらの措置は、場所の危険性の観点から危険防止を図るための措置として義務付けられているものです。このため、労働者以外の者であっても、当該場所で作業に従事する者には等しく適用されるべきものであることや、これらの措置は指揮命令に基づくものではなく、当該場所を実態として使用・管理している者の権原に基づいて行うものであることから、労働者以外の者も、これらの措置義務の対象に追加されたものです。
2立入禁止の方法としては、必ずしも事業者が常時監視する必要はなく、禁止する旨を見やすい箇所に表示する方法も認められます。立入禁止の方法はバリケードの設置やロープ、柵等の設置、出入口の施錠などの方法から実態に即したものを選定すればよいものです。
なお、特定の場所において作業に従事する者とは、作業の内容如何にかかわらず、その場所で何らかの作業(危険有害な作業に限らず、現場監督、記録のための写真撮影、荷物の搬入等も含まれる。)に従事する者をいい、例えば次に掲げる者が含まれます。
① 当該場所で何らかの作業に従事する他社の社長や労働者
② 当該場所で何らかの作業に従事する一人親方
③ 当該場所で何らかの作業に従事する一人親方の家族従事者
④ 当該場所に荷物等を搬入する者
また、「作業場において作業に従事する者」と規定しているのは、「労働者」とは異なり「作業に従事する者」は措置義務の主体である事業者と直接雇用関係を有するとは限らないことから、立入禁止等の対象となる者を特定する必要があるためであり、対象範囲を限定する趣旨ではありません。
3立入禁止を表示で行う場合は、対象となる全ての者に確実にその旨が伝わることが重要であることから、見やすい箇所に分かりやすく表示する必要があります。他方、事業者が、表示その他の方法で立入りを明確に禁止している場所について、作業に従事する者が当該表示等を無視して、当該場所に立ち入った場合において、その立入りについての責任を当該事業者に求めるものではありません。加えて、労働者以外の者に対して事業者が明確に退避を求めたにもかかわらず、当該者が退避しなかった場合は、退避しなかったことの責任を事業者に求めるものではありません。
4事業者は、作業指揮者を定め、当該指揮者に労働者の立入りを禁止させることがありますが、労働者以外の作業に従事する者と、作業指揮者との間には指揮命令関係が存在しないことを踏まえて、作業指揮者の義務への追加ではなく事業者の直接の義務として、「労働者以外の作業に従事する者」の立入りを禁止することとしています。事業者がその義務を果たすための方法として、作業指揮者に当該措置の実施を命じることにより労働者以外の作業に従事する者に対する立入禁止の措置を講ずることも認められるものです。
労働安全衛生規則
(搭乗の制限)
第151条の13 事業者は、車両系荷役運搬機械等(不整地運搬車及び貨物自動車を除く。)を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。ただし、墜落による危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
(荷台への乗車制限)
第151条の72(1項省略)
2作業に従事する者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。
(搭乗の制限)
第151条の81 事業者は、コンベヤーを使用する作業場において作業に従事する者を運転中のコンベヤーに乗せてはならない。ただし、作業に従事する者を運搬する構造のコンベヤーについて、墜落、接触等による危険を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。
2前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、運転中のコンベヤーに乗ってはならない。
クレーン等安全規則
(搭乗の制限)
第26条 事業者は、クレーンを使用する作業場において作業に従事する者を、クレーンにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。
第27条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、クレーンのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人)を乗せることができる。
2事業者は、前項の搭乗設備については、墜落による危険を防止するため次の事項を行わなければならない。
一搭乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。
二労働者に要求性能墜落制止用器具(安衛則第130条の5第1項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。)その他の命綱(以下「要求性能墜落制止用器具等」という。)を使用させること。
三作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該請負人に対し、要求性能墜落制止用器具等を使用する必要がある旨を周知させること。
四搭乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。
3労働者は、前項の場合において要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(搭乗の制限)
第72条 事業者は、移動式クレーンを使用する作業場において作業に従事する者を、移動式クレーンにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。
【解説】
1搭乗禁止の方法としては、必ずしも事業者が常時監視する必要はなく、禁止する旨を見やすい箇所に表示する方法や口頭で確実に伝達する方法が認められます。
2悪天候時の作業禁止の方法としては、必ずしも事業者が常時監視する必要はなく、禁止する旨を見やすい箇所に表示する方法や口頭で確実に伝達する方法が認められます。
労働安全衛生規則
(修理等)
第151条の15 事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタッチメントの装着若しくは取外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
一作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。
二第151条の9第1項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロック等の労働者の使用状況を監視すること。
【解説】
本規定は、車両系荷役運搬機械等の修理等の状況の監視対象を労働者に限定していますが、これは、労働者以外の作業に従事する者と作業指揮者との間に指揮命令関係が存在しないことを踏まえ、対象を明確化したものです。なお、労働者以外の作業に従事する者について、作業指揮者が監視することを妨げるものではありません。
(積卸し)
第151条の62(1項省略)
2事業者は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(昇降設備)
第151条の67(1項省略)
2前項の作業に従事する者は、床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
(積卸し)
第151条の70(1項省略)
2事業者は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(作業指揮者の選任及び職務等)
第420条(1項省略)
2事業者は、前項の作業を行う箇所に当該作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
【解説】
事業者には、特定の業務又は作業を行う場所について、請負関係の有無にかかわらず、労働者以外の者も含めて立入禁止等の措置を講ずる義務が新たに課されますが、これら立入禁止等の義務が及ぶ場所の範囲は、当該業務又は作業が行われている一定の区切られた範囲(当該業務又は作業の影響が直接的に及ぶと考えられる合理的な範囲)です。
なお、当該範囲は、今回の改正により、これまで労働者に対する義務が生じていた範囲と、異なるものではありません。
(悪天候時の作業禁止)
第522条 事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。
【解説】
事業者は、悪天候のため特定の作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならないとされていましたが、労働者以外の者も含めて、悪天候時に当該作業を行わせてはならないこととなりました。悪天候時の作業禁止の方法としては、必ずしも事業者が常時監視する必要はなく、禁止する旨を見やすい箇所に表示する方法や口頭で確実に伝達する方法が認められます。
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第33号)及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第104号)が、3月28日(火)に公布されました。
1 昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大
貨物自動車に荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置や保護帽の着用が義務付けられる貨物自動車の範囲が、最大積載量2トン以上の 貨物自動車となります。(改正前は最大積載量5トン以上)
ただし、最大積載量が2トン以上5トン未満の貨物自動車で保護帽の着用が義務づけられるのは、あおりのない荷台を有する貨物自動車、平ボディ車、ウイング車など、荷台の側面が開放できるものや、テールゲートリフターが設置されている貨物自動車で、テールゲートリフターを使用するときに限られます。
2 テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化
貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育の対象となります。令和6年2月1日以降は、以下のカリキュラムによる特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。
【特別教育のカリキュラム】
学科教育
| 科目 |
範囲 |
時間 |
| テールゲートリフターに関する知識 |
テールゲートリフターの種類、構造及び取扱い方法 テールゲートリフターの点検及び整備の方法 |
1.5時間 |
| テールゲートリフターによる作業に関する知識 |
荷の種類及び取扱い方法 台車の種類、構造及び取扱い方法 保護具の着用 災害防止 |
2時間 |
| 関係法令 |
法令及び安衛則中の関係条項 |
0.5時間 |
実技教育
テールゲートリフターの操作の方法について、2時間以上
-
運転位置から離れる場合の措置の一部改正
走行の運転位置とテールゲートリフターの運転位置が異なる貨物自動車で、原動機を停止するとテールゲートリフターが動かせなくなるものは、運転者が運転位置を離れるときの原動機停止義務とテールゲートリフターを最低降下位置に置く義務が適用されなくなります。ただし、ブレーキを確実にかけるなどの逸走防止措置が必要です。
なお、本規則改正は、令和4年8月26日に取りまとめられた「陸上貨物運送業における荷役作業の安全対策に関する検討会報告書」を踏まえたものです。検討会報告書はこちら。 また、今回の改正を受けて、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」も改正されました。改正後のガイドラインはこちら。
今後、当協会ホームページ、広報誌「陸運と安全衛生」及び各都道府県支部を通じて、随時情報提供してまいります。


 荷役ガイドラインの解説
荷役ガイドラインの解説 荷役ガイドラインのあらまし
荷役ガイドラインのあらまし 荷役災害防止設備等の事例集
荷役災害防止設備等の事例集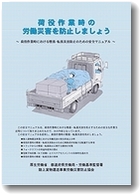 荷役作業時の墜落・転落災害防止のための安全マニュアル
荷役作業時の墜落・転落災害防止のための安全マニュアル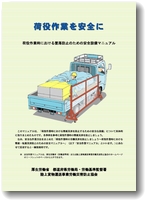 荷役作業における安全設備マニュアル
荷役作業における安全設備マニュアル 陸運業における重大な労働災害を防ぐためには
陸運業における重大な労働災害を防ぐためには 「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」リーフレット
「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」リーフレット フォークリフトの作業開始前点検の進め方(DVD)
フォークリフトの作業開始前点検の進め方(DVD) トラック荷台からの転落を防ぐために
トラック荷台からの転落を防ぐために
